【ばんそうAI】質問力が上がり、問いが深まるコンサルAIの可能性

株式会社ばんそう 代表取締役 松田 克信
中堅・中小企業が直面する「相談相手がいない」「情報が届かない」といった課題。そこに、新しいかたちの“経営支援”として現れたのが、『ばんそうAI』だ。
「AIの本質は“対話を通じて思考を整理する”こと」そう語る代表の松田氏が見つめるのは、AIが質問力を鍛え、中堅・中小企業の意思決定が変わる未来だ。コンサルタントの思考プロセスが詰め込まれたAIは経営判断を支えられるのか?【前編はこちら】
鹿児島での偶然の出会いが、構想に命を吹き込んだ

――どのようにして『ばんそうAI』と鹿児島大学の関係が始まったのですか?
松田:そうですね、少し長い話になるのですが、きっかけは銀行時代の先輩との再会なんです。横浜支店時代に仲の良い先輩の一人が鹿児島出身で。ずっと仲が良くさせていただいていて「実は会社を作ろうと思っている」と話したとき、彼が「俺も手伝いたい」と言ってくれたんです。
うちの会社は「将来的には、47都道府県すべてに拠点を持ちたい」という話をすると、「じゃあ、俺が鹿児島を担当するよ」と彼が言ってくれて「3日間時間をくれ」と。で、実際に鹿児島に一緒に行き、鹿児島大学や行政機関を紹介してくれたんです。
――鹿児島大学との接点も、その旅の中で生まれたのですか?
松田:その先輩が、大学時代に鹿児島県人寮に入っていて、そこで一番仲が良かったのが、今は鹿児島大学の法文学部で教授を務めている先生でした。そのご縁で「飲みに行こう」という話になって、これが、鹿児島大学との最初の接点になりました。
その先生に「AIを活用して中堅・中小企業を支援したい」と話すと、先生が「AIに詳しい教授がいる」と。それで、先生が何人かの教授を紹介してくれて、その中に高橋哲朗准教授がいました。
――高橋先生とは、どんなところで意気投合されたのですか?
松田:高橋先生が興味を持ってくれた点は「回答を出さないAI」というところかなと思っています。「今までのAIは“何かを調べるための道具”という発想」「回答を求めるときにAIを使うという発想」だったのが、「AIで質問力を育てる」という発想は新しくて面白いと言ってくれました。そこから一緒に共同研究・開発をやってみようという話になったんです。
――高橋先生の専門分野はどういった領域ですか?
松田:高橋先生は、鹿児島大学大学院理工学研究科で、自然言語処理を専門に研究されています。私自身の経歴も少し似ているところがあって、面白い出会いだったなと思っています。
私自身は、もともとは物理学者になりたかったんです。大学受験のとき、物理系の学科で出願したのですが、予期せず、第二志望としていた生物工学科に合格しました。あんまり真剣に生物工学科のことを考えずに記載したので、生物工学のことを何も知らずに入った学科でしたが、脳神経などを研究している研究室があったりして、意外と面白かったんですよ。とはいえ、都会の誘惑にも負け、勉強になかなか身が入らず、大学卒業に6年かかったんですが。(笑)
でも、そんな経験があったからこそ、「LLM」(大規模言語モデル)の話や、脳の構造・思考のメカニズムに自然と関心を持てたというのはあります。高橋先生と出会って「LLMって人間の脳や思考の構造に近い」って話をしたとき、改めて「もっとちゃんと勉強しておけばよかったな」とも思いました。
――まさに“スティーブ・ジョブズのConnecting the dots(点と点をつなげる)ですね。
松田:そうなんです。「ニューラルネットワーク」(人間の脳内の神経回路網を人工ニューロンという数式モデルで表現したもの)ではないですが、“ネットワーキングの力”、つまり複数の要素をつないで大きな価値を生む力が、共通して働いているのかもしれない、と感じています。高橋先生とも、そういう力に引き寄せられて、出会ったんじゃないかな、と。
【高橋哲朗氏と松田 克信氏の対談動画】戦略コンサルタントの知見を詰め込んだ『ばんそうAI』の誕生
――ばんそうAIについて教えてください。
松田: 中堅・中小企業の経営者は、往々にして「うちの会社、このままでいいのか」というモヤモヤを抱えています。たとえば「売上が落ちている、でも何をすればいいかわからない」といった悩みです。社内で話をしても、結局「何をやるか」が見えてこない。そこに必要なのが「壁打ち相手」としてのディスカッション機能なんです。
会社が抱えている「本当の課題は何か?」「何を解決すべきか?」という問いに対して、未来のことなので答えはない。でもその答えのない問いに向き合い、議論を重ねていくプロセスこそが大事なんです。
私たちは、そのプロセスを「AI」と「人」のハイブリッドで実現しようとしています。
「課題を仮説ベースで抽出」し、「その課題を明確に言語化」して、それを「ロジックで分解」して「真因を突き止めていく」いく。それが戦略コンサルティングの本質であり、これが 『ばんそうAI』の最も重要な価値の一つだと思っています。
質問力を育てるAI──ロジックツリーで導く対話
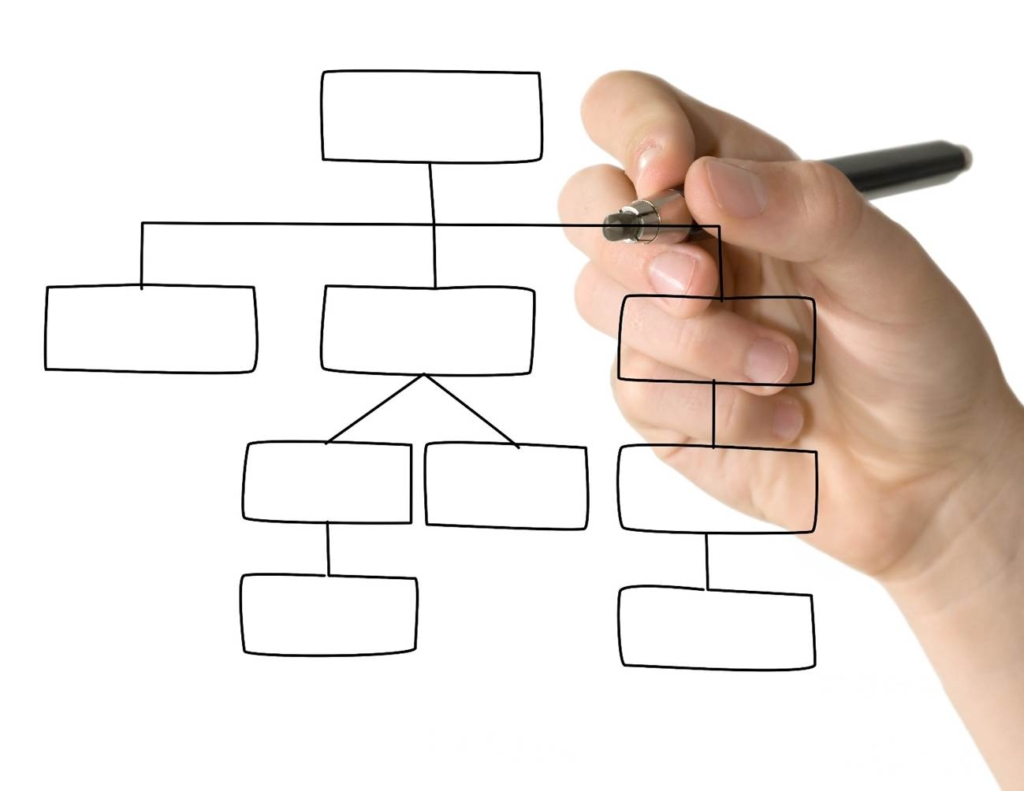
―― AIは使う人の経験値が大きく影響しますね。
松田:おっしゃる通りです。みなさんもChatGPTを使っていると思いますが、「Google検索の延長線上」で捉えている人が多いのではないでしょうか。つまり、調べたいことがあって、それを聞いて答えをもらうという受動的な使い方です。
AIを使いこなすためには、「良い質問を投げる力」が求められます。『ばんそうAI』は、この質問力を支援するために設計されています。
――質問力とはどのようなものでしょうか。
松田:たとえば、「なんとなく困っているんだけど…」という曖昧な状態のユーザーに対しても『ばんそうAI』はロジックツリー*に沿って、丁寧に対話を重ねていきます。
ビジネスの現場でロジックツリーは「知っている」と言うひとは多いですが「活用できる」ひとは少ないです。たとえば「人間をロジックツリーで分解して」と言われても、ほとんどの方が詰まってしまうのではないでしょうか。
「どこに困っているのか」「困りごとの要素は何か」「AとBのどちらに近いか」「細かく分解するとどうなるか」といったロジックツリーの問いを通じて、少しずつ問題の輪郭を明らかにしていく。そうすることで、ユーザー自身が「何に困っていたのか」に気づけるよう導く。それが、『ばんそうAI』の基本思想です。
*ロジックツリー: 課題を階層的に分解し、論理的に整理するフレームワーク。全体像や本質的な原因を見えやすくし論理的に整理できる。原因分析や解決策の立案、意思決定プロセスの明確化など、業務改善や複雑な課題を構造的に理解する目的で使われる。
――まるでコンサルタントが隣にいるようですね。
松田:そうなんです。まさにコンサルタントが「ホワイトボードを前にして行う議論」をAIで再現しようとしているんです。つまり、コンサルタントの思考プロセス自体をAIに移植して、育てていこうとしています。
「LLM(大規模言語モデル)というのはまるで人間の成長を見ているよう」とよく話します。たとえば、ChatGPTが最初に登場した頃は、小学生レベルの頭脳だったものが、今では東大の入試問題を解けるレベルにまで進化しています。いうなれば「脳力」の進化です
でも、「脳力」が進化するだけでは仕事には通用しません。たとえば、ハーバードのMBAを上位で卒業した人が全員コンサルティング業界で成功するわけではありません。成功確率は高いと思いますが、必要なのは鍛えた脳への“職業訓練”なんです。
これはAIにもまったく同じことが言えると考えています。ChatGPTのようなLLMがどれだけ「頭が良い状態」にあっても、それを実際の職業にフィットさせるための訓練、つまり、プロフェッショナル思考のインストールが欠かせません。コンサルタントのような「仮説思考」「構造化」「優先順位付け」などを丁寧に“仕込んで”いっています。LLMを職業人として育てる。それが『ばんそうAI』が目指す姿なんです。
「問いを深めるAI」をマルチエージェントで
――AIを職業人のように育てるという発想は斬新ですね。
松田:『ばんそうAI』で最初に手をつけたのは、戦略コンサルタントの「幅広く」「深く」物事を捉える能力、つまり、“スーパージェネラリスト”を育てることでした。我々が構想しているのは、いわば、“スーパージェネラリスト”の「戦略AI」です。
コンサルティングの本質は「仮説思考」と「構造化」にあると思っています。たとえば「エレベーター業界の市場がどうなるか」と問われて、全く知らない業界だったとしても、他業界の構造と照らし合わせて仮説を立てられる。それが“スーパージェネラリスト”の思考です。
――スーパージェネラリストの思考をどうやって実現するのですか?
松田:この思考をAIで実現するには「ロジカルシンキング」を正しく教える必要があります。その代表的な思考法がロジックツリーですね。ロジックツリーを使って構造を掘り下げていけば、「何が課題で、どこが本質なのか」が自然と浮かび上がってくる。私たちはその思考法をベースに、AIを設計しているんです。
――具体的に教えてください。
松田:たとえば、AIに「うちの新製品が売れない」と相談されたときに「売れない理由を教えて」と聞くと、よくある答えは返ってきます。でもそれだけでは不十分で、そこから自社の状況に照らして「何が真の原因か?」を深掘りする必要がある。
そのプロセスを可能にするのが、ロジックツリーとイシューツリー**の行き来なんです。ロジックツリーはいうなれば、「網羅的に要素を分解するための思考」。イシューツリーは「課題の本質は何かを掘り下げていく思考」この二つの思考法を自在に行き来しながら、「問いを深めるAI」を目指しています。
**イシューツリー:特定の課題を論点として整理し、その解決策を系統的に導き出すフレームワーク。特定の課題を深く分析し、課題解決につなげる目的に使われる。各論点に対してイエス・ノーで答えることで、仮説が正しいかどうかを検証できる。
――「問いを深めるAI」を実現するのは簡単ではなさそうですね。
松田:まさにそこが難しいところです。LLMはいま、知識の要素分解までは得意なんですが、「その会社にとって何が最優先か?」という問いへの答えを導き出すには、まだ壁があります。なぜなら、今のAIはその会社固有のデータを持っておらず、かつ思考の深掘りができないからです。
私たちのAIの発想は「質問をうまくできるように誘導するAI」なんですよ。だからこそ、AIに仮説思考と優先順位のつけ方を教え、問いの重ね方を訓練していく必要がある。私たちはそれをマルチエージェント型AI(複数のAIエージェントが協力してタスクを遂行するシステム)で実現しようとしています。
中堅・中小企業の経営者が気軽に使える「壁打ち相手」

――質問をうまくできるように誘導するという発想は非常にユニークです。
松田:「AIによって人間の質問力が上がる」ということを目指しています。
LLMの活用する大きな意味は“対話を通じて思考を整理する”ことにあると思うんです。LLMは、シンプルに言えば、確率統計的に「次に来るであろう適切な言葉」を予測する仕組みです。その性質を使えば、「なぜこの答えが出たのか?」を考えるきっかけになり、質問の精度や思考の深さが自然と鍛えられていきます。その繰り返しが“職業的訓練”になると私たちは考えています。
――職業的訓練をさせる際に、取り入れている工夫はありますか?
松田:プロンプトはコンサルタント経験者が設計しています。私自身も含めて、何千パターンもの仮想問答を行いながらテストを繰り返しています。コンサルタントには多少“クセ”があるんです。ロジカルシンキングという基本的なスキルは共通ですが、コンサルタントによって思考のスタイルが多少違う。
それと同じで、誰が設計したかによってAIの出力の質や傾向が変わってきます。将来的には「どういうコンサルタントが設計したAIコンサルタントか?」で選ばれる時代が来ると思っています。
――『ばんそうAI』のプロンプトは、どのようにされているのでしょうか?
松田:多くは私たちが仮想のシチュエーションを想定して作っています。より多くのシチュエーションを想定することで、汎用性のあるプロンプトに仕上げていく形です。
実在しない仮想の質問に対して、私をはじめとするコンサルタント経験者たちが、ひたすらテストを重ねる、訓練のプロセスを積み重ねて進めています。
――価格設定や将来の利用イメージについても教えてください。
松田:最終的には、数千円台でサービス提供をすることを想定しています。なるべく多くの人に使ってもらえる価格設定にしたい。中堅・中小企業の経営者が気軽に使える水準を目指しています。
中堅・中小企業の価値を生み出す
――日本の中堅・中小企業がどんな状態になるのがゴールですか?
松田:「ゴールを目指す」というよりも「ずっと続けていくもの」だと捉えています。テクノロジーと人間本来の力をうまく融合させることで、中堅・中小企業が一社でも、社会に「価値」を生み出すことを最大化していくよう支援したいんです。
たとえば、ホンダのように「移動手段を提供することで、世の中の人たちが幸せになった」と思われる価値だったり、ソニーのように、「人々の娯楽や創造性に貢献して、人生が豊かになったと感じてもらえるような価値」だったり。そんなふうに、社会の中で確かな意義を持ち、様々な課題を本質的に解決する会社を、私たちはお客様と一緒に作っていきたいと思っています。
特に中堅・中小企業の方々に、「ばんそうさんと一緒にやれて本当に良かった」そういう声が自然と出てくるようになると、すごく嬉しいですね。
【後編おわり】
【松田 克信 プロフィール】

株式会社ばんそう 代表取締役CEO
東京三菱銀行(現 三菱UFJ銀行)を経て、大手コンサルティングファーム(Deloitte Tohmatsu Consulting、Roland Berger、PwC Advisory、三菱UFJリサーチ&コンサルティング)で戦略コンサルタントとしてプロジェクトに従事。
2021年9月、株式会社ばんそうを設立し代表取締役CEOに就任。
経営の悩みに寄り添い、課題を発見し、相談者の気づきを促すAIプロダクト『ばんそうAI』の開発・提供を行う。






