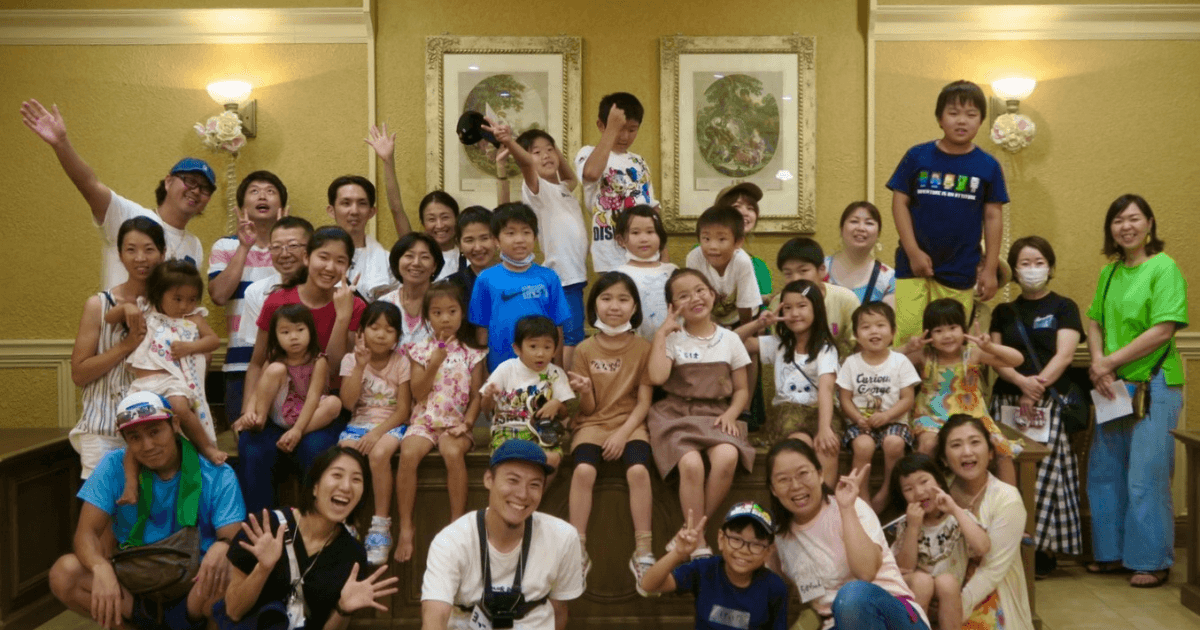【メタジェンセラピューティクス 中原 拓】腸内細菌に感じた“大きな物語”。博士キャラに憧れた経営者が目指すイノベーション

メタジェンセラピューティクス株式会社 代表取締役社長CEO 中原 拓
2020年、順天堂大の医師と慶応大、東工大の研究者らにより立ち上げられたメタジェンセラピューティクス株式会社。CEOを務めるのは、バイオインフォマティクス研究者としてのキャリアを経て、米国でベンチャー企業の立ち上げに参画し、その後ベンチャーキャピタリストも務めた、異例の経歴を持つ中原 拓だ。そんな中原氏に、メタジェンセラピューティクスの創業ストーリーを聞いた。
メタジェンセラピューティクスは何を目指すのか

ーーまず初めにメタジェンセラピューティクスの事業について、教えてください。
中原 私たちは、「マイクロバイオームサイエンスで患者さんの願いを叶え続ける」というミッションを掲げて、その実現のために事業を進めています。
ーーマイクロバイオームとは…?
中原 マイクロバイオームというのは腸内や皮膚、口腔など、体のいたるところにある「細菌叢(さいきんそう)」、つまり細菌のかたまりを意味します。なかでも特に腸には数千種、38兆個にも及ぶ非常に多くの細菌が存在し、人によって大きく異なる細菌叢を形作っています。
近年、この腸内細菌叢の研究が大きく進展し、がん、潰瘍性大腸炎、パーキンソン病、アレルギー等、さまざまな疾患との関連が明らかになってきました。この腸内細菌叢を活用することで、「医療」と「創薬」の世界にイノベーションをもたらし、新しい未来を創ることが、私たちの目指す大きな目標です。
世界トップレベルの研究者、医師。ドリームチームが集まった

ーー御社は同じく腸内細菌叢の研究を事業のコアとするスタートアップ、メタジェンが母体となって創業されました。創業の経緯を教えてください。
中原 もともと私は前職の時代にメタジェンのCEOである福田 真嗣と知り合い、メタジェンの事業について相談を受けたり、アドバイスをしていました。腸内細菌叢について学んでいくうちに「腸内細菌叢で医療と創薬をやるべきだ」と考えるようになり、メタジェンで「チャレンジしてほしい」と言い続けていたのですが、「それならぜひ、中原さんが社長になって進めてくれませんか」と言われたのです。
最初は悩んだのですが、創業メンバーと出会い自分が代表になってこのチームで夢をかたちにしよう、そう思いました。それがメタジェンセラピューティクスの始まりです。当社のファウンダーは4人いますが、私を除いた3人は、腸内細菌を用いた医療のトップランナーである医師や、福田をはじめとする世界トップレベル腸内細菌叢の研究者たちです。まさにドリームチームです。興奮しましたね。
メタジェンセラピューティクスは、メタジェンの子会社としてスタートしましたが、いまは独立した別の会社として経営しています。一言でいえば、メタジェンは腸内細菌叢の知見を「健康な人」が健康維持に取り組む予防のための事業を行うのに対して、私たちは「病気の人」を治療するための事業、すなわち「医療」と「創薬」にフォーカスしています。
腸内細菌で、「医療」と「創薬」の世界にイノベーション

ーー腸内細菌叢を活用した「医療」と「創薬」というのは、具体的には?
中原 まず「医療」の事業では、「FMT(腸内細菌叢移植)」という医療技術の社会実装を進めています。
FMTは健康な人の便から腸内細菌叢を抽出し、病気の人の腸に移植する治療法で、感染性腸炎(難治性Clostridioides difficile感染症)に対して非常に高い治療効果をあげたことから世界的な注目を集めました。最近ではオーストラリアでFMTが医薬品として承認されるというエポックメイキングなニュースもありました。しかし、日本ではまだ治療を受けられる医療機関が数少なく、私たちは事業を通じてその社会的な基盤を作っていきたいと考えています。当社のCMOであり順天堂大医師の石川 大は、日本でのFMTの第一人者です。
FMTの社会実装には、腸内細菌叢を必要とする患者さんと、腸内細菌叢を提供するドナーをつなぐ「腸内細菌叢バンク」の構築が不可欠です。私たちは順天堂大学との連携により「腸内細菌叢バンク」を構築し、FMTに用いる便の収集と細菌叢溶液の作製をサポートしていきたいと思っています。
ーーなるほど、骨髄バンクの腸内細菌版といったところでしょうか。創薬の方は?
中原 そうですね。もう一つの柱、「創薬」については、FMTを応用した細菌叢そのものを薬とする新しい医薬品や、アカデミアシーズを活用した腸内細菌叢のメカニズムに働きかける薬の開発を目指しています。
従来の医療の常識からすると「うんこを移植するだけで、本当に病気が治るの?」と思う人もいると思います。これまでの一般的な低分子化合物を材料とする医薬品開発では、候補物質の探索から、前臨床試験、臨床試験に10年ほどの歳月と数百億円の費用がかかるのがふつうでした。しかしFMTを起点とした創薬では、FMTによって腸内細菌叢を正常化することで薬効が出るか確認してから開発を始められるので、従来の創薬のプロセスに比べてより効率的に有効性のある薬を開発できる可能性を秘めています。まさにイノベーションだと思っています。
「博士キャラ」にあこがれた幼少期

ーー中原さん自身、イノベーションを起こしたい、そんな想いをずっと抱いていたのでしょうか。
中原 んーどうでしょう。小学生ぐらいのときからずっと「将来は博士になりたい」と思っていました(笑)。レゴブロックで遊ぶのがとても好きで、いつも組み立てていましたね。当時のレゴは今のように、スターウォーズやディズニーとコラボしたりといった商品はありませんでしたので、自分で想像力を働かせながら家や建物を作るのを楽しんでいました。
ーー小学生の時から博士になりたかったんですか!
中原 はい、テレビアニメとか子供向けの本に、よく登場する「博士キャラ」に憧れたんです。主人公のことを一歩引いた立場から、該博な知識と発明で手助けするような博士の存在がかっこいいなと思いました。映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』に出てくるドクのような、ちょっとエキセントリックだけれど天才的な博士になりたいなと思っていました。私の父が研究者だったこともあります。私は北海道大学農学部の出身ですが、うちの家系には北大農学部に進学する人が多く、父も北大で研究者になってから、酪農学園大学に勤務していました。
ーーなるほど、研究者という存在が身近にいたわけですね。
中原 そうですね。あと大きなインパクトがあった体験としては、私が中学生のときに父がデンマークに1年間留学して、それに家族でついていったことです。父の留学期間中、私と妹は、向こうの公立中学・小学校にそれぞれ通うことになりました。デンマークの公用語はデンマーク語ですが、向こうの人たちはみんな英語ができるので、片言の英語で友だちや先生とコミュニケーションをとる必要がありましたが、とくに不自由なく、楽しく過ごせました。その時の経験で「どこに行っても何とかなる」という楽観的な人生観が育まれたと感じます。
日本に戻ってからは、札幌開成高校に進学しました。「博士になりたい」という夢はずっと抱き続けていたので、大学に行って研究の道に進むことは決めていました。進路を選択する上で大きな影響を受けたのが、昨年お亡くなりになったジャーナリスト・立花隆さんが書かれた『精神と物質 分子生物学はどこまで生命の謎を解けるか』という本です。
ーーノーベル賞をとられた利根川進さんと、立花隆さんの対談本ですね。精神や心の働きを、当時の最先端の分子生物学の知見を紹介しながら解説する内容に、興奮した記憶があります。
中原 そうです、それまでは物理学が好きだったのですが、あの本を読んで、「これからはバイオが面白いかもしれない」と思ったんです。それで北海道大学の農学部に進学して、バイオの研究を行うことにしました。
実験に挫折し、バイオインフォマティクスの世界へ

ーー入学後は、どんな研究テーマに取り組んだのですか?
中原 北海道でよく採れるとら豆というマメ科植物の、でんぷんをつくる酵素の研究です。植物は日の当たらない夜中にでんぷん合成を行っています。でんぷん合成が一番活性化するのが太陽が昇る直前の時間帯なのですが、それで学生時代は毎朝夜明け前に起きて、畑に行ってはとら豆を収穫して分析するという実験を繰り返していました。ところがその作業で気づいたんですが、自分は実験がめっちゃ下手で、向いていなかったんですね。
ーーそうなんですか(笑)。
中原 はい、実験の結果も思ったようにでなくて、失敗ばかりでした。「畑に出て実験をするのは合わないな。もうちょっと頭脳労働のほうに比重を置いた研究をしたい」と考えるようになりました。その結果として、現在の私の專門であるバイオインフォマティクスの研究に進んだというのが経緯です。バイオインフォマティクスというと、生命科学と情報工学の掛け算により、コンピュータ上でビッグデータなどを利用しながら生命のメカニズムに迫る
というのが一般のイメージです。しかし実はバイオインフォマティクスの研究にはもう一つの太い幹がありまして、それが「進化学」なんです。
ーー進化学というと、ダーウィンから始まる進化についての学問ですか?
中原 はい、そうです。「生物はどこから来て、どうして今のような形になったのか」を解き明かすのが進化学になります。日本は昔から進化学の研究に強かったのですが、1980年前後に木村資生の中立説が発表されて以降DNAの配列解析が進化学のメインツールになり、コンピュータを使った解析がどんどん進み、大規模にデータを集めて解析する研究手法が一般的になりました。
私はその進化学のほうのバイオインフォマティクスの出身で、北大のあとに進んだ名古屋大学の大学院では、タンパク質の進化の過程について研究を行いました。具体的には、生物の体を作るタンパク質というのは、生きていく中でさまざまな「糖鎖」と呼ばれる物質がくっついて修飾されることで機能が変化するのですが、その糖鎖を合成する酵素の分子進化をタンパク質の立体構造ベースで解析していました。
ーーなるほど。中原さんが進化学に興味を惹かれたのは何かきっかけがあったのでしょうか。
中原 それにはハッキリとした理由がありまして、進化学には「ストーリー」があることが面白いな、と思ったんです。
ーーおお、このメディアの名前にもある「ストーリー」ですか。
中原 はい、学部時代に生物学を専門的に勉強するようになってから、生物学というのは「個別性の塊」だなと強く感じたんです。例えば、細胞外のシグナルを細胞核に伝えるMAPカイネースという物質がありますが、それがリン酸化修飾する酵素が、MAPカイネースカイネースになって、さらにそれをリン酸化する酵素はMAPカイネースカイネースカイネースという呼び名になります。
ーー呪文みたいですね(笑)。
中原 本当に分子生物学って、そういう暗号みたいな言葉をひたすら覚える学問なんですよ。法則性があまり感じられなくて、『三国志』に山ほど出てくる武将が誰と戦って、誰が負けて誰が勝ったかみたいな感じで、とにかく物質同士のつながりをランダムに覚えなきゃならないんです。それがどうも面白くなくて、「生物学ってつまらんな」と感じ始めていたときに、生物の進化という大きな物語を探求する進化学に出会ったんです。
進化にはある種の方向性、法則性が存在します。また自分が研究していたタンパク質という物質は、アミノ酸がつながった鎖が一定の決まりでフォールディング(折りたたみ)されることで特定の形となり、機能を発現しますが、そのフォールディングの仕方にも進化にともなう法則が見て取れるんですね。そういう生物の歴史を貫く「大きな物語」に惹かれたことが、進化学に関心を抱いた最大の理由でした。
腸内細菌に感じた「大きな物語」

ーー中原さんがメタジェンセラピューティクスの創業を担うことになったのも、腸内細菌に「大きな物語」を感じたからでしょうか。
中原 それはあると思いますね。腸内細菌叢という、まだまだ未解明の部分が沢山残っている領域が、人間の健康や病気になるメカニズムに大きな影響を与えていることに、大きな関心を覚えます。
ーーバイオインフォマティクス研究者としての経験が、いまの経営に生きていると思うことはありますか。
中原 それはよく感じます。バイオインフォマティクスって、サッカーで例えるなら、「ミッドフィルダー」のような役割なんです。シュートしてゴールを決めるストライカーは実験によって仮説を検証する研究者で、当社では石川や福田がそれにあたります。
サッカーでもそうですが、研究でも「すごいゴール」を決めるためには、「最高のパス」をもらう必要があるんです。バイオインフォマティクスによって実験では不可能な回数のシミュレーションを行い、十分に確度の高い「仮説」を見つけてから実験を行うことで、成功の確率は飛躍的に高まります。当社の山田は日本を代表するバイオインフォマティシャン、すなわちミッドフィルダーで、私もかつては同じポジションでプレーしていたので、彼のプレーにはいつも惚れ惚れしています。
私のいまの会社における役割は、彼らが最高のシュートを決められるように、あらゆる面でのサポートを行うことだと考えています。
【中原 拓 プロフィール】
メタジェンセラピューティクス株式会社 創業者・代表取締役社長CEO
バイオインフォマティクス研究者としてキャリアを始め、のちに自身が関わった研究で2008年に北海道大学発ベンチャーを製薬企業とともに創業、約6年間ニュージャージー州でバイオインフォマティクス責任者を務める。その後、日系大手消費財企業、米系ベンチャーキャピタル、日系ベンチャーキャピタルで新規事業・スタートアップ投資を行う。
2020年にメタジェンセラピューティクス(MGTx)を創業しCEOとして日本のアカデミア・企業発のマイクロバイオーム医療・創薬シーズの事業化を目指して奮闘中。MGTx本社は山形県鶴岡市、東京事務所はCIC東京内で本人は札幌在住。
札幌市バイオビジネスアドバイザーとして地元のバイオイノベーションエコシステム構築活動も行う。
Photos: Yuto Kuroyanagi
Writer: Yutaka Okoshi
Editor: Ayako Iwatani
関連記事